![]()
人の才能というものは磨けば必ず光の出るものであるけれども、其の素質によって或程度までしか光りの出ないものもあり、殆ど底止するところを知らないものもある。
書に於ける天才は根気よく磨くことによって始めて生まれるものである。手先の器用不器用の如きは努力の前には極めて権威のないものである。
練習の上に無駄を省いて習字の効果を出来るだけ多くすることが唯一の書道達成の法であって、腕の錬磨を第一要件とする書道に、機械的達成法などあろう筈は断じてない。
1.用筆形体共に正しく奇癖なもの
2.品位と雅致に富めるもの
3.筆意の明瞭なるべきこと
先ず楷書を学んで、しっかり根底を築く。行草も その用筆の根源は皆楷書から出ている。筆法も最も完備している。
楷書の次に草書を学び、それから行書に移るのを以て得策と考える。草書の用筆に熟してしまえば、その中間にある行書は自然にできあがる。
その後、仮名を学び、次に調和体を究め、さらに隷なり篆なりに及ぶ。
まずは大字によって運腕の練習をなし、漸次小字にと及ぶべきで、最初から小字ばかり書いていると委縮して腕の暢びのないうらみがある。
古法によらないですべて自由にやっていこうとする傾向があらわれた。新境地を開こうとすること自体は悪くはないが、昔から「温故知新」、
故法を探求するのも新しい境地を開拓する過程であって、古法を無視したり、反逆して進もうとする如きは明らかに行き過ぎ。
幾千年の研究工夫を無視して、根本的な改革を企図すれば、そこには恐らく改悪があるのみである。先ず古来の書法を学んでかからなければならない。
全く師そっくりで、落款を取ってしまえば誰の書か見分けのつかない、何等個性を発揮することのない、一生他人の後塵を追って終わるもの(を奴書という)。
しかし「学ぶ」は「真似る」の転訛語。師の筆意を会得するのは書道に於ける進歩。一家の法すら会得し得ないものが衆長をとるなどとは全く烏滸の沙汰。
若し一家の法を得て、それに案じ衆体を究めることをためさず、個性を発揮することをなくして一生を終わるの者のごときが、それこそ真の奴書である。
 側(ソク、点) 勒(ロク、横画) 努(ド、縦画) 趯(テキ、はね) 策(サク、右上がりの横画) 掠(リャク、左はらい) 啄(タク、短い左はらい) 磔(タク、右はらい) |
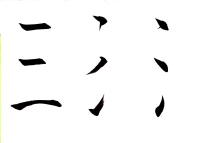 横画の変化 仰勢(上にそるもの) 平勢(まっすぐ) 覆勢(下にそるもの) |
|
|