 第1巻 9~10 藤原楚水著 省心書房
第1巻 9~10 藤原楚水著 省心書房 第1巻 9~10 藤原楚水著 省心書房
第1巻 9~10 藤原楚水著 省心書房書道吏上空前の巨観
漢朝一代は儒学を崇尚し、六体書をもって士を取り、想像以上に書道を重視した。故に書画彫刻等の芸術もまた従って大いに発達したが、特にこの時代に於ける書体の変化は尤も複雑を極めた。
後漢の第12代皇帝霊帝(169-188)は自ら書を好まれ、広く天下の能書者を集め、鴻都門にこれを見引したが、その時、集った書家は数百人に達し、書名をもって各種の文献上にその名を見るものもまた百人を下らない。
秦に起った古隷の一体なども、前漢の終より後漢にかけて八分書として完成され、更に章草、飛白、行書等も皆この時代に成った。
漢代著名の書家
漢代に於いて書に名ある者には蕭何・司馬相如・張安世・張彭祖・厳延年・史游・李長・張敝・杜鄴・劉向・孔光・揚雄・爰礼・陳遵・杜林・衛宏・曹喜・杜度・班固・徐幹・賈魴・王溥・崔瑗・崔寔・許慎・尹珍・張芝・張昶・朱賜・羅暉・姜詡・蘇班・蔡邕・劉陶・劉徳昇・張超・師宜官・梁鵠・毛弘・左伯・苟爽・朱登・徐安于・王綺・王瞻・羅盻・劉懆・李巡・蔡邕等極めて多いが、歴史上不朽の名を留めているものは概ね後漢の世に出で、特に、曹喜・杜度・崔瑗・張芝・蔡邕・師宜官・梁鵠などはその最たるものである。
曹喜。宇を仲則といい、扶風の平陵に生まれ、建初年間(78-83)に秘書郎になつた。篆隷を工にし天下に名を得た。
杜度。字を伯度といい、京兆杜陵の人。御史大夫延年の曾孫で、章帝のとき斉の相となった。その草書は建初年間、章帝に重んぜられ、当時草聖といわれた。
崔瑕。字を子玉といい、琢郡安平の人。早く詞人の親を亡くしたが、学を好んでよく父の業を伝え、当代の文人は均しくこれを宗とした。文辞を工にし、尤も章草を善くし、兼ねて小篆で妙であった。その書蹟には張平子碑があった。
張芝。字は伯英、張昶の兄。燉煌酒泉の人。初め杜度、崔瑗の手法を学んで章草を善くし、後その作風を変じた。一字一字が上下連続し、その体勢は一筆になって、気脈が通い、行を隔てていても恰もつながっているようなので、一筆書または一筆飛白書の称がある。
張芝はまた八分を善くし、行書を工にし、弟の張昶もまた隷、八分を工にし、草書は兄に似た。
蔡邕。陳留圉の人。字を伯噌といい、建寧中(168-172)、郎中校書に、初平元年(190)、左中郎に拝せられ、高陽郷侯に封ぜられた。書法、絵画、音楽、詩文等、漢代芸術の大家であると共に、その学は術数、天文等にまでも及んだ。
また鴻都門を訪れた際に、工人が亜帚(刷毛帚、墻を塗る器具)をもって字を書くのを見、帰って飛白書を創ったといわれ、後世飛白の祖と仰がれ、また八分書の神のようにいわれる。
師宜官。南陽の人。八分書の大家で、かつて霊帝が天下の能文、能書家を徴したとき、数百人の応徴者のうち、八分書の第一名をかち得た。耿球碑はその書するところと伝えられる。
梁鵠。安定烏氏の人。宇を孟皇といい、師宜官と同時に八分書で名を馳せた。初め孝廉に挙げられ、幽州刺史となり選部尚書になった。
碑の起源と碣の相違
漢代の書家の真蹟は、今日すでにみることは出来ない。近年漢晉の木簡が発見されたが、これとても漢人の墨蹟であるというだけで、当代の名書家の手筆ではない。
従ってこの時代の名家の遺蹟としては、ただ碑碣の類の拓本についてこれを見る外はない。
石刻でも前漢のものは少なく、またこの時代の書体は古隷から漸く八分に演進せんとせる過渡期にあったため、書としてもほとんどまだ一格をなしていなかった。故に漢碑の文宇といえば、後漢時代のものに限られた観がある。
この時代に入ると、八分書が全く完成され、多くの刻石が見られるようになり、この風は益々盛んとなった。
が、魏晉の両朝は屡々立碑を禁じ、その後も南朝はやはり碑禁が厳しかった。
碑の起源を以って、廟に犠牲をつないだ石柱と、墓穴に棺槨を下すために用いた木柱の二種に置いている。
『説文解字』には、碑と碣との区別は、『説文』にいう竪石、特立石。『後漢書』の注の方と円、或は『唐六典』の定めるところなど、いろいろ異説はあるけれども、実際においてはその限界はあまり明瞭ではなく、『語石』にあるように多く混同されている。
しかし豊碑短碣等の語もあるから、大体、方形のものを碑といい、円形のものを碣または特立石であるともいう。
漢碑と書人
漢碑の伝世するものは、毎碑面貌を異にし、各々その妙を極め、その書風は極めて大まかに見ても、方整(鴻都石経 尹宙 魯峻 武栄 鄭固 衡方 劉熊 白石神君)、流麗(韓勅 曹全 史晨 乙瑛 張表 張遷 孔彪 孔宙)、奇古(夏承 戚伯著)の三つの系統に属すべきものである。
漢碑には多くは書者の姓名を記さない。かつ年代が遠くして書者を考究する手がかりがないために、世人は往々典籍の中に書者を求め、漢碑中の絶品は、殆んど蔡邕、梁鵠の生存年代中に成り、さらにこの二人の名が特に高かったが為に、多くは書者をこの二人に付会した。その信ずべきでないことはいうまでもない。
そのうち蔡邕の書と推定できるものは、郭有道碑と、熹平石経だけである。
郭有道碑は建寧2年(169)正月に建てられ、蔡邕37歳のときにあたる。
古くより蔡邕の書とされているが、原石は久しく佚して伝わらない。
現存している拓本は皆翻刻であるから、原石の蔡邕の書蹟が如何なるものであったかはわからない。
熹平石経は、すべてが蔡邕の書ではあるまいが、その中に蔡邕の書いたものが存していたことは疑うべくもあるまい。
この外では劉熊碑、史晨碑などが蔡邕書と伝えられるけれども信ずるに足らない。また、夏承碑は全く後人の偽託である。
西嶽華山廟碑の筆者については、古来種々の説を生んだ。(今では北周の趙文淵とされる。)
石は明の時代に地震で壊れすでに失われ、またその拓本も極めて少ない。ただ著名なものが三つある。即ち長垣本、関中本(華陰本 北京故宮博物院蔵)、四明本(北京故宮博物院蔵)で、いずれも北宋以後の拓本である。そのうち長垣本が最も古く、字も多い。先年中村不折翁の秘笈に帰した。
篆・隷その他いずれの書体であろうとも、その書体の盛行した最初の時代のものが最もすぐれ、ついで漸時堕落するのが普通であるから、小篆は秦を中心とし、八分は後漢を中心として学び、他は参考程度にとどめるべきである。
漢碑の書の源流と分流
漢碑は、一碑毎にその面目を異にし、書として絶妙を極めていないものはなく、その中の一碑を専攻しても、一家を成せるが、その書品には自らまた甲乙がないわけではない。
書の優劣を論じて、何種類かの階級にわけることは、歴代その撰に乏しくない
漢碑のように各碑みなその面目を異にし、その体勢が同じでないところにおのおの妙の存するものにあっては、その優劣をきめることは容易でないから、寧ろ各碑各様の趣を味い、自ら好むところについて学ぶ外はない。
主なる後漢の碑碣について
漢中太守鄐君開褒斜道摩崖刻石(永平6年・63)
陝西省褒城県の北、石門にある巌壁に刻したもので、摩崖と呼ばれ、碑と称すべきものではない。
宋の時に発見された後も、これを訪うものは希であった。
永平は明帝の年号で、この刻は後漢の最初のものであるのみならず、その字数の多いことも珍らしく、その書また石勢によって縦横奇斜の趣を恣にしている。
その書は篆勢をもって、隷をつくらんとし、また篆より八分に変わろうとするの趣を備え、渾樸蒼勁、到底まねできないものがある。漢隷を研究するものの見逃してはならないものである。
益州太守北海相景君碑(漢安3年・144)
この碑について王元美は、隷法故に自ら古雅といい、孫月峯は華山・孔宙・張遷・魯峻・趙君の諸碑と並び列し、隷法大約古勁といい、康有為はその書をもって駿爽なりといっている。
司隷校尉楊孟文石門頌(建和2年・148)
陜西省褒城県北の石門の摩崖に刻したもの。石門は褒斜の谿谷にあって、その巌壁には、鄐君君開通褒斜道刻石を始め、北魏の王遠の石門銘その他、漢魏以来の古刻が苔の間に隠見しているという。
この石門頌もその中の一つで、特にその書の縦横剄抜と称せられ、如何にも飄逸な書体で頗る逸趣に富んでいる。
魯相乙瑛置孔廟百石卒史碑(永興元年・153) 孔廟-2 (kohkosai.com)
孔廟置守廟百石卒史碑とも、魯相請置孔廟卒史碑とも、魯相乙瑛碑とも、百石卒史碑とも、単に乙瑛碑ともいい、或は孔麻碑とも呼ばれている。
この碑の書は華山廟碑に似て非常に素樸雄強の趣があるので有名である。
李孟初神祠碑(永興2年・154)
出土がおそく、欧・趙・洪等宋人の著録には見えない。
永興二年の年の字の垂脚が長く垂れている。
石門頌の裂紋がこれを刻した当時既にあったものか、或はその後に生じたものかを今日では推定することは困難であるのみならず、石門頌の升の宇、誦の字なども垂脚は非常に長く、殆んど二画を過ぎている。これは石門頌のみに限らず、漢人の書には往々見るところで、五鳳二年刻石を始め、甕や木簡等にも年の字の垂筆は非常に多い。
孔謙碣(永興2年・154) 孔廟-2 (kohkosai.com)
孔謙碣は、石は極めて短く、他の碑とは非常に異なっている。これが碑と呼ばずして碣と言われる所以である。
孔君墓碣(永寿元年・255) 孔廟-2 (kohkosai.com)
孔君墓碣とも孔君墓碑とも呼ばれている。
数百年を経た今日においては益々剥渤が多く、存字はいくつもないが、その書法は蒼勁をもって称せられているもので、漢隷を学ぶには参考とすべきものである。
魯相韓勅造孔廟礼器碑(永寿2年9月・156) 孔廟-2 (kohkosai.com)
魯相の韓勅が造立し、その著録に現れた名称は一様ではなく、修孔子廟器表、韓明府孔子廟碑、漢魯相韓勅造孔廟礼器碑、韓勅造孔廟礼器碑、韓明府叔節修孔廟礼器碑とも呼ばれている。
礼器碑の書は漢分中にあって、最もその形の整つたもので、歴代の多くの評書家は推して漢分第一となし、神品をもって目する人も少なくない。同時にこの碑は、平正の中に奇険を蔵し、厳密の間に疎秀を寓しているから、その点を注意しないと流媚に陥る危険があると注意している。
郎中鄭固碑(延熹元年4月・158)
今は磨滅が甚だしいが、はじめに尚「君諱固、字伯堅、著君元子也。」等の字が明らかに現存し、又『隷釈』にはその全文を掲げて、「延熹元年二月十九日。詔拝郎中噂非其好也。以疾錮辞。未満二期限。従其本規。乃遘凶愍年卅二。其四月廿四日遭命殞身。痛如之何。」の文がある。
泰山都尉孔宙碑(延熹7年5月・164)孔廟-2 (kohkosai.com)
この碑の書は漢碑中、最も飛動の妙を極めたものであるが、字法がやや縦逸に過ぎているから、これを学ぶにはその点に注意して、軽薄に流れないようにしなければならない。
額の篆書も後人の補刻ではなく、漢人の手に成ったものであろう。
封竜山頌(延熹7年・264)
碑の出土は道光26、7年(1846、1847)の間で、『集古録』・『金石録』は勿論、近く『金石萃編』にも著録がなく、『寰宇訪碑録』にも其名を逸し、『補寰宇訪碑録』に至って初めてその名がみられる。
西嶽華山廟碑(延熹8年4月・165)
この碑が特に有名になったのは嘉慶13年(1808)阮元の所蔵に帰して以後のことである。
華山廟には延熹以前にも古碑があった。延熹(158 - 167年)のときに刻したもので、明時代の初め、尚その石は存在したが嘉靖34年(1555)の大地震に毀れたともいわれ、或は県令が廟を修する為に砕いて砌石にしたともいう。
今廟中にあるのは後に銭宝甫(坤銭)が重刻したもので、文字は完好である。
第一、四明本(北京故宮博物院蔵)
阮元の得たものが四明本で、朱竹君の子の小河と、その所蔵の関中、四明、長垣の各本を携えて竜泉寺に会し、おそらく同時の拓であろうという帰結を得た。
第二、関中本(華陰本 北京故宮博物院蔵)
明のころは陜西の東雲駒、雲雛兄弟の家に伝わり、後、郭宗昌の所蔵に帰し、清時代に入って後は王山史、張力臣、凌如煥、黄文槎諸家の逓蔵を経て朱竹君の有に帰し、嘉慶(1796-1820)のとき曲阜の孔氏の蔵するところとなり、次いで梁蓙林の蔵に帰した。この本もまた他の二本と共に後に端方の蔵に帰した。
第三、長垣本
明末に長垣の王文蓀(鵬冲)の家に伝わった。文藤は王覚斯の親戚で、この本には覚斯の跋がある。清初に商邱の宋漫堂が得るところとなり、宋漫堂、邵子湘の詩、朱竹地の跋、その他題跋が非常に多く、継いで同邑の陳伯恭の蔵となり、嘉慶2年(1797)、成親王の詒晉斎に帰し、更に劉燕庭、端方等に逓蔵されて、最後に我が中村不折翁の秘笈に帰した。
長垣本は三本中の最旧拓で、偏旁の損欠僅に十許字、他は全部完好である。
竹邑侯相張寿残碑(建寧元年5月・168)
張竹邑碑は武城県(山東)にあるが、『集古録』以外の宋人の著録ではわずかに『隷釈』に全文が載っているに過ぎない。
碑文簡質、字法古雅、具に漢人の風格があり、鄧石如の隷書も実にこの碑に学ぶところが多かったことが知られる。
この碑を著録するものは極めて多い。
衛尉卿衡方碑(建寧元年9月・168)
この碑は、漢碑中でも著名なものの一つで、明時代では文徴明が専らこの体を学び、清朝においては孫星衍、伊秉綬の諸家がこれを学んだといわれ、後の張遷碑と共に、漢碑中の古樸派の一種に属すべきものである。
魯相史晨祀孔子奏銘(建寧2年3月・169)孔廟-2 (kohkosai.com)
この碑は俗に前碑後碑と称しているが実は一石両面刻で、一面には奏請の章を、一面には饗礼のことを叙している。
史晨饗孔廟後碑(建寧2年・169)
魯相晨孔子廟碑、魯相晨謁孔子冢文、魯相晨等奏出王家穀祠孔子廟碑、史晨碑、史晨前碑、史晨後碑ともいう。
この碑は乙瑛、礼器の諸碑と共に、伝世の漢碑の中最も完好なるものの一つであり、その書は蘇東坡の表忠観碑の祖とするところであるともいわれ、その書の妙を称するものは歴代少くない。
この碑をもって蔡邕の書とする説もあるが、もとよりこじ付けの説に過ぎない。
武都太守李翕西狹頌(建寧4年6月・171)
この頌は巌壁に刻した所謂摩崖で、碑ではない。その旁に黽池五瑞図を刻し、君昔在黽池云々と八分書をもって題している。
この書は寛博遒古、高巌立壁に称えるに足る。
博陵太守孔彪碑(建寧4年7月・171) 孔廟-3 (kohkosai.com)
この碑については、歴代の著録の多くは文字、史実の考証を主とし、その書を評したものは極めて少い。
この碑を著録するものは非常に多く枚挙し難い。
武都太守李翕析里橋郁閣頌(建寧5年・172)
陜西略陽の摩崖に刻されたもので、漢時の刻は剥落が甚だしく、今存するのは後世の重刻であるとの説もあるが、全部が重刻ではなく、原刻の一部分を補鑿したものであると見る説が多い。
執金吾丞武栄碑(無年月) 済寧市博物館 (kohkosai.com)
『庚子銷夏記』に、「石全くは磨滅せるにあらず。文既に簡質、字またかくの如し。自らこれ後漢の風格、珍とすべき也」とあり、楊守敬も、「淳古にして峭健、流麗にして円結、漢碑の佳品にしてまた分法の正宗たり。字少なきを以ってこれをいい加減にするしかない」としている。
司隷校尉楊淮表記(熹平2年月・173)
石門頌と同じく褒谷の磨崖に刻したもの。
書法は重厚で、古雅な風姿を持っている。褒谷の磨崖には長く伝統を持つ一種の書風があった。
幽司隷校尉魯峻碑(熹平2年・173)
楊守敬の『平碑記』に「豊膜雄偉、唐の明皇、徐季海はまたこれより出づ。而れども肥濃太だしくしてこの気韻なし」とある。
今その大部分は磨滅して読みがたいが、この碑を著録するものは宋以後非常に多くして枚挙しがたい。
玄儒先生婁寿碑(熹平3月正月・174)
この碑の原石は久しく失われて伝わらず。宋の時の旧拓本を伝えるのみである。或はいう石は尚存すれども、幾んど剥勒して字なきに至っている。
古来諸家のこれを評したものは少なくないが、原拓を見たものは多くない。碑の全文は『隷釈』に載せられている。
聞憙長韓仁銘(熹平4年11月・175)
この碑は久しく失われ、金の正大年間(1224-1231)に榮陽の令李天翼が訪得し、これより再び世に現われるようになった。
清俊秀逸にして一筆の塵俗の気なし。品格当に百石卒史の上なるべし。
予州従事尹宙碑(熹平6年4月・177)
明の嘉靖(1522-1566)中に泊水が増水し、河岸が崩壊して地中から出たもので、石も非常に完好である。
碑は土中より晩出し、文字尚完く、結体遒勁にして猶篆籀の遺を存せり。漢隷中にあってはまた別に一格なり。
白石神君碑(光和6年・183)
この碑には光和(178-183)の紀年があるけれども、その書風から見て、或は後人が旧文をとって刻したのか、または再刻ではあるまいかと疑っているものもある。この碑の重刻なること本より考えるべきである。
翁方綱は、「この碑の漢刻たるや疑うべきものなし」としている。楊守敬も漢石説をとっているが、唯その書は漢隷中の最下のものと見ている。
郃陽令曹全碑(中平2年・185)曹全碑 (kohkosai.com)
明の万暦年間(1573-1819)の出土で、その拓本は早く我国にも舶載された。故に我国で漢隷といえば殆んどこの碑に限られたかのような観があった。
この碑の書は円美遒麗であるため多くの人に喜ばれた。
この碑は漢隷中にあって遒媚の一派に属すもので、雄厚さに欠けているところがあるけれども、漢碑中の代表的傑作の一つであることは誰にも異論のないところである。
蕩陰令張遷表頌(中平3年・186)
この碑は明末の出土にかかり、古くはその著録を見ない。
碑文中に訛字異文が多いので、或は贋物か重刻であろうと疑ったものもあったが、『隷弁』、『金石図』、桂馥の『札樸』でも、漢石であることを疑っていない。
『平碑記』にも、「篆書は体多く長し。この額は独り扁なり。また一格也。碑陰は尤も明晰にしてその用筆巳に魏晉の風気を開けり。この源は西狭頌より始まり、流れて黄初三碑の折刀頭となり、再変して北魏の真書の始平公等の碑と為る。」とある。
安陽漢刻四種(年月欠)
安陽漢刻四種というのは、『金石萃編』に子游残碑・劉君残碑・元孫碑・正直碑と称している四つの残石である。
子游残碑は、僅に十二行、劉君残碑は石二塊を存し一石は六行、他の一石は五行、元孫碑は四行、正直碑は七行で、多くても八十余字、少ないものは二十余字を存するだけである。
完好なときの碑の大きさも字数も明らかでないがいずれも漢隷を学ぶものの参考とすべきものである。
一旦出土した安陽漢刻残石四種は、『循園金石跋尾』の記すところによれば、二十余年また亡失して所在がわからない。今、安陽古跡保存所にあるものは、民国以後に重刻したものであるとのことである。
子游残碑
この残石は嘉慶年間(1796-1820)に訪得したもので、古くは著録に見えないが、その書は渾樸古厚、風神饒で、一鱗片甲と雖も自ら貴むべきものがある。
近年この碑の上截十二行、毎行八字のものがまた出で、その石は天津の姚氏に蔵せられている。
元孫碑
『安陽県志』に、「右、漢元孫碑は西門君廟の糯田の間に棄置せられたり。徐方于は柴望之景堂、趙仲原敞と偕に尋出し、僅に遺字四行を得たり。前に云く遺孤奉承と。字は蓋しその家の式微を述べたるならん。故に継ぐに大兄早終を以ってす。これ哀むべしと為す也。書の秀蘊なる当に奉じて神品と為すべし。」といい、
趙在翰は、「この碑、結体は孔彪・李孟初と相似、斌媚これに過ぎたり。」と評している。
正直碑
首行に正直の字あるを以って題して正直碑という。
この碑の書は在翰の跋に「宇画の端整なる尹宙に近く、而して鋩利はこれに過ぎたり。これを習えば方に漢隷の真正の法門を得、野狐禅の悪道に堕入するに至らざる也。」と見え、他の三碑とは非常に面目を異にしている。
楊守敬の『平碑記』に、「正直の一石、余は疑う漢刻にあらじ。当に西晉北魏の間にあるべし」とある。
劉君残碑
一つに碑側の文字をとって「歳在辛酉三月之碑」ともいう。
その書は古雅寛博にして、結体は蒼頡廟碑と略相似ている。唯、碑側の歳在辛酉三月十五の八字は、字の大きさも書も似ていないから、この部分は或は後人の題記と見るのが正しいであろう。
画像の起源
書学が漢において異常なる発達をしたように、絵画もまた毛延寿・劉褒.張衡.趙岐等著名の作家が輩出して長足の進歩を遂げ、その取材も非常に多方面かつ広汎に及んだ。
その目的は、専らこれを政教に利用するにあった。当時は政治の理想を唐虞に置いたので、その絵画も多くは古の明君、名儒あるいは忠臣、孝子、烈女等の、歴史上の故事を描くにあった。
この風は漢に始まったのでなく、その淵源は頗る遠かった。
夏・商・周に於いて既に絵画を礼教に利用することが行われ、黄帝は蚩尤の像をえがいて動乱を鎮圧し、舜は衣冠を描き、禹は九鼎を鋳てその上に鬼神百物の形を彫飾した。周にはこの類さらに多く、宮廷の旌旗に、王は日月の形をえがき、諸侯は蛟竜を或は熊虎、鳥隼、亀蛇を描き、また明堂の門塘に、堯舜桀紂の像を描き、楚の廟および祠堂に、天地山川神霊碕璋古賢怪物の行事をえがいたことなど、所謂壁画もこの時代に於いて早くその発達を見た。
秦は始皇の初年、諸侯を破る毎に、必ず画人をしてその宮室を摸写させ、後年宮殿を造営する参考としたことは、その用意の一端が窺われる。天下統一の後は、大いに土木を興し、咸陽に於いて阿房宮を建築し、その雄偉壮麗であったことは千古を称羨させた。
始皇は四方を経営し、西域地方は勿論、インド方面とも既に陸上貿易が行われたが、漢の武帝に至ってしばしば北方の匈奴を征し、遠く西域諸国と交通し、元狩元年(前122)には、博望侯張騫を西域に使せしめ、西は安息(ペルシア地方)に至り、南は身毒(インド)に至ってその文化を輸入し、後漢の明帝もまた武帝の志を継いで国威を西域に振い、かつて永平8年(65)郎中蔡惜、博士王遵等18人をインドに遺わして仏教を研究させた。これより以後、西域との交通はいよいよ頻繁となり、西方諸国の文化を輸入することが盛んになった。このことは絵
画の上にも自然大きな影響を与え、取材の上にも相当大きな影響があったものと思われる。仏画もまたこの時代に於いて中国に入った。
漢代の画像と遺物
漢代に於ける絵画は、その目的とするところは依然として一般臣民を教化するにあったので、必要上壁画の形式をもって行われた。
漢代の画学は書学と並んで急速にその進歩を見、漢代独特の雄大古拙なる画風を大成した。
漢以前の絵画は、前記少数の出土の真蹟の外は、これを石刻に求める外はなく、石刻としては石室、石闕の類に求める外はない。
石室と石闕
石室とは廟墓の前に建てるところの石造の祠堂をいい、その目的は専ら展墓享奠の用に供するにある。一にまた食堂ともいう。
石闕には廟祠の前に建てるものと、墓道の上に設けるのと二種がある。秦漢時代には宮殿の前に於て多くは二つの台を築き、上に楼観を建て、中央を欠いて道と為し、これを闕と称した。また象魏ともいいその壁に法令などを貼付し、公布の場所にあてた。
廟祠または墳墓の前の石闕は、この象魏を模倣して作ったもので、その遺物の現存するものは、後漢に入って始めてこれを見、隋唐以後には全くその跡を絶っている。更に祠堂石室の大部分が、殆んど山東省内に限られているのに反し、石闕は多く蜀中に存在していることは、また一奇と称せざるを得ない。
孝堂山その他の石室
石室、石闕の壁画は死者の冥福を祈り、子孫の鑒誡に資するの目的をもって描かれ、或は鬼神に奉事するの意を持たせ、その題材も吉禽・祥獣・瑞物・聖賢・名士・烈女の類が多いがこれによって当時の風俗、制度の概略を窺うことができる。
現在のところ最も著名で、かつ、画の工緻なものとしては、孝堂山祠及び武梁祠の二つを挙げねばならない。
孝堂山祠は山東省肥城県の西南或は西北、孝里鋪の小丘上の古墳の前にあり、彼の名高い二十四孝中の一人郭巨の建てたもので、堂後の古墳は即ち孝子の母の墳墓であるといい伝え、古くは郭巨石室と称し、附近の居民の尊敬を受け、最も完全に保存されている。
郭巨については異説もあるが、後漢の順帝以前のものと推定されている。
この石室の画象は、筆痕を陰刻にし、その手法には尚前漢の名残りがあり、後漢の画象が陽刻であるのとは全くその趣を異にしている点などから見て前漢末期のもので、漢代のこの種の遺物中に於いてはその時代が最も古く、且完全に保存され、研究資料として非常に貴重なものであるが、文字としては殆んど見るべきものがな
い。即ち文字の研究方面よりすれば時代は稍下るが、武梁祠をもって代表的のものとしなければならない。
洪福院画象
凡て三石。唯、一石に成王・周公・魯公三人の題字あるのみ。
射陽石門画象
凡て二石。孔子見老子象である。孔子中に居りて西面し、老子左に居りて東面し、一弟子、孔子の後にありて西面せり。済洲学宮中の象とは同一でない。
朱鮪墓石室画象
男女燕饗の有様を描がき、「朱長舒之墓」井に鮪の字などがある。
李剛墓祠画象
車馬駒騎歩卒を描がき「君為荊州刺史時」「東郡」「郡太守」「烏桓」「梁高行」「梁使者」等の文字を存す。
伏尉公墓中石画象
凡て入石。人物禽獣等を図し「伏尉公」「右将軍韓侯子本」「高陵侯」「曲闕侯」等の文字を存している。
魯峻墓祠壁画象
凡て二石。車馬人物を図し、「祠南郊」「従六駕出時」「君為九江太守時」「功曹史」等の字を存す。
李翕黽池五瑞図
西狭頌の前にあるもので「黄竜・白鹿・嘉禾・木連理」を描かき各題字あり。又一人喬木の下に盤を捧げるの状を描かき「甘露降、承露人」と題せり。左方に「君昔在二黽池殉脩二晴嵌之道叩徳治精通。致二黄竜白鹿之瑞一故図二画其像一云」の題字がある。
武梁祠と刻石の文字
武梁祠の石室は、後漢の桓帝の建和元年(147)の建造にかかった。その所在地は今の山東省嘉祥県の東南の武宅山。武氏は商の武丁の後裔で、順帝、桓帝時代には任城の望族であった、この石室は武氏数代の墳墓の前に建てられたもので、その著名なる碑には、従事武梁碑、呉郡丞武開明碑、敦煌長史武斑碑、執金吾武栄碑がある。
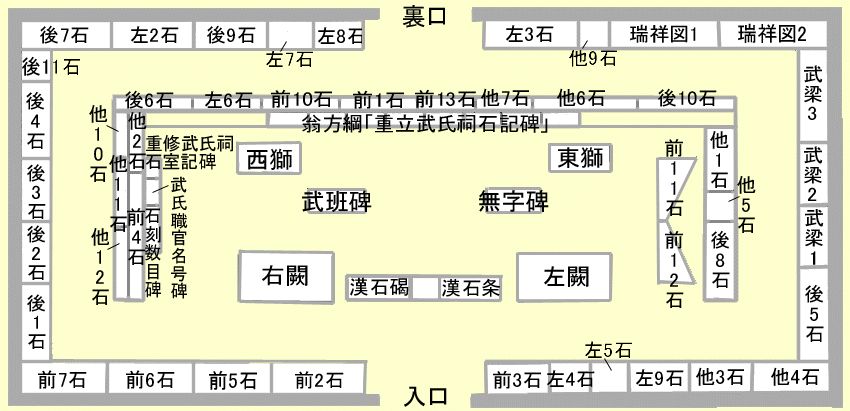
武梁祠画像は黄易に訪得されて再び世に出たもので、その発見の場所によってこれを区別しているが、総じていえば武梁祠画像と称する。
武梁祠堂画像 武氏祠墓群石刻 (kohkosai.com)
全て三石、一石五層に図画し、その中の三層に題字があり、二層には題字がないが、武梁祠画像中で題字の最も多いのはこの三石である。
第一石
第一層には
中央に神人を描き、両脇に、雑物奇怪・山神海霊等これを環繞している。題字なし。
第二層には
第一列に伏羲・女蝸を描き「伏戯倉精。初造王業。画卦結繩。以理海内。」この一行16字を題し、
第二列には、右に向う一人を描き「祝誦氏無所造為。未有耆欲。刑罰未施」と一行15字を題し、
第三列には俯視して手に耒耜を執る一人を描き「神農氏因宜教田。辟土種穀。以振万民。」この一行15字を題し、第四列には、肱を張った一人を描き「黄帝多所改作。造兵井田。垂衣裳。立宮宅。」と一行16字を題し、
第五列には拱手右向する一人を画き「帝??高陽者。黄帝之孫。而昌意之子。」と一行15字を題し、
第六列には拱手向前する一人を描き「帝?高辛者。黄帝之曾孫也」と一行11字を題し、
第七列には両手を右に向けて右向する一人を描き「帝堯放勲。共仁如天。其智如神。就之如日。望之如雲」と一行10字を題し、
第八列また帝堯と同形の一人を描き「帝舜名重華。耕於歴山・外養三年」と一行13字を題し、
第九列には左向する一人を描き「夏禹長於地理。脉泉知陰。随時設防。退為肉刑。」の一行18字を題し、
第十列には、一人右向して戈を執り、二婦人の上に坐せるを描き「夏桀」と一行字を題し、
第三層の
第一列には、一人機前に坐し、一人跪坐せるを描き、上に「曾子質孝。以通神明。貫感神祗。箸号来方。後世凱式。□□撫網」の六行十四字を題し、下に「讒言三至。慈母投杼」の八字を横に題し、
第二列には、一馬、一車と三人を描き、前に「子騫後母弟。子騫父」と二行8宇を題し後に「閔子騫与仮母居。愛有?移。子騫衣寒、御車失捶」と19字を二行に題し、
第三列には四人を描き、上に「老莱子楚人也。事親至孝。衣服斑連。嬰児之態。令親有驩。君子嘉之。孝莫大焉」と六行30字を題し、下に「?子母。?子父」の6字を平列し、
第四列には木像を左に描き、拱手して像に跪く一人と婦人とを描き「丁蘭二親終歿。立木為父。鄰人仮物。報乃借与。」と四行18字を題し、
第四層の
第一列には四人を描き「管仲。斉桓公。曹子刻桓。魯荘公。」と四人の左に分題し、
第二列には一人冠服するを描き、一人前跪し、二人侍立するを描き「二侍郎。専諸炙魚。刺殺呉王。」と11字を三行に題し、また「呉王」と一行字を題し、
第三列は一人怒髪左向し、一人その腰を抱き、一人地に伏し、一人驚避の状あるを描き「荊軻。樊於其頭秦武陽。秦王。」と題し、
第五層には
乗馬の人物を描き、ここには題字がない。
第一石に描くところの大要は右の通りで、いずも歴史上の故事を描き、もって鑑誡たらしめようとしたものである。第二石、第三石とも大体同様である。
武氏前石室画像
全て十四石『平津読碑記』に十五石とあるのは、表裏に画像があるため更にこれを一石として計算したものである。その第一、第十四の二石には題字がない。その他には子路、此丞卿、門下功曹、君車、門下游徼、主簿車、令車等の題字があるが、その字数は祠堂画象に比べば遙に少い。
 此騎吏 前石室第5石 調聞二人 |
 荊軻 前石室10石第1層 |
 伯游 前石室第7石 |
 功曹車 前石室第6石 |
 賊曹車 前石室第6石 |
 令庫 前石室第4石 |
 伯游 前石室第7石 |
 主記車 前石室第6石 |
 門下游徼 前石室第4石 |
 尉卿車 前石室第6石 |
 門下游徼 前石室第4石 |
 游徼車 前石室第6石 |
 門下游徼 前石室第4石 |
武氏後石室画像
全て九石。『平津読碑記』には十石という。題字倶に磨滅している。石柱に武家林の三字あり。黄易云く、辺幅に隠々として八分書「中平等」の字あり、諦視すれば尚弁ずべしと。
武氏左石室画像
全て十石。題字のあるはただ第一石のみである。
武氏石室祥瑞画像
全て二石。毎段祥瑞、草木、禽獣の状を描く。題宇は多く泐している。
武氏石室新出画像
全て九石。『平津読碑記』に云く、一石。上下倶に漫?し、中に武氏祠の三大字、八分書ありと。
孔子見老子画像
一石。もと武宅山にあったが、黄易等によって済寧州学に移置さた。
武梁祠にはもと三石室があったが、その刻画の諸石は発見当時、黄易、李東琪、李克正、高正炎等相謀って捐銭七十五万一千を募り、深さ約一丈四尺、広さ約五尺の祠堂を新につくり、尽くこれを一堂の内に収めて壁上に篏置し、武斑碑を室中に立て、孔子見老子の一石はこれを済寧学宮の明倫堂に移した。翁方綱にこの記がある。
石闕の文字
石闕の文字で、その時代の古くて有名なものは、所謂三闕と呼ばれる漢の嵩嶽太室、少室、開母廟の三つで、皆、篆書で書かれ、篆書を学ぶには是非とも参考とすべきものである。
嵩山三闕銘
中国の後漢代の元初5年(118)から延光2年(123)にかけて建てられた。3つとも全て現在も建造地に残されている。ただし、少室・開母廟は廟が廃され、石闕のみが残されている。
この外、漢の石闕としては、堂谿典嵩高山石闕銘、路君闕画象、董君闕画象、范君闕画象(府君神道の四字を存す)、郡君闕画象などあるが、或は文字が已に磨滅し、或は文字小さく、或は文字全く無く、書の研究上参考とすべき価値あるものは殆んどない。
両漢における遺書の蒐集と校合
石経とは石に刻した経典のことである。それには儒家の経典、道家の経典、仏家の経典の三種あるが、普通に石経というときは儒家の経典を刻したものを指すようである。
儒家の経典を石に刻したのは、漢の熹平石経が最初で、魏の正始、唐の開成、西蜀の孟氏、北宋の嘉祐、南宋の紹興、清の乾隆と歴代その刻があるが、多くは官の刻するところであり、私家の刻するところは極めて少い。
経典を石に刻する目的は、仏家にあっては多くは功徳の為にし、或は経典の保存弘通を目的とするが為に、深山幽谷や、人跡未踏の磨崖などに刻した。
儒教の場合はこれと異なり、その目的とするところは全く経典の文字を正して定本を作ることだから成るべ
く多く人の眼につくところに立てるのが普通である。
両漢における教育の状態
漢初の君臣は、概して学問の素養がなかったか
石経を刻するに至った原因
刻経の年代と名称
熹平四年(一七五)は霊帝が石経の刻を命ぜられた年であり、光和六年(一入三)は刻が完成してこれを立てたときと見て誤りがなかろう。
るべく、その間に要した年月は前後九ヶ年であるが、瞿中溶の『漢石経考異補正』には、何故かその間を二十六年とし、
漢石経はその刊始の年号に従ってこれを熹平石経といい、また当時通行の八分書をもって書いてあるので、これを今字石経ともいっている。
石経の破壊と移動
漢の石経が立てられて間もなく霊帝の中平元年(184)、黄巾の乱が起こり、初平元年(190)、討伐の兵を起こした董卓は洛陽の宮廟を焼き、献帝を奉じて都を長安に遷した。この時石経もまた兵火の災に遇い、損欠を免れなかった。
魏の黄初元年(220)に至って、漢石経の破壊されたものを補ったが、晉の永嘉(307)のころにはまた殆んど崩壊した。『魏書』によれば、北魏になってまた多く破棄されたようである。
このように漢の石経は相ついで破壊され、その僅かに残ったものも東魏の武定4年(546)に至って洛陽より灘に移した。この時その石の大半を失った。その残存のものについては、それ以来相当の保護が加えられた。
次いで北周の大象元年(579)に至って、また鄰より洛陽に移され、隋に至って更に洛陽より長安に移された。ところが、そのとき大部分が廃棄されたものと思われる。
石経の書体について
漢の熹平石経と魏の正始石経とは同じ場所に立てられ、同じく移し変えられ、壊し損なわれたため、両者を混淆し著録しているものが少くない。
書体については、漢の石経を八分一体であるといい、または古文、篆、隷の三体であるとか、三体を三石に一体ずつ分書したとの説もある。
書者について
筆者については、一般に蔡邕の書と信じられているが、宋以後発見された残石には蔡邕のほか、『礼記』では馬日?(石編に單)・蔡邕、『公羊』では堂谿典・馬日? (石に單)・趙?(?に或)・劉弘・張文・蘇陵・傅槙、『論語』では左立・孫表などの説がある。
蔡邕一人の書であるとの説
この説は、『後漢書』蔡邕伝の外にも非常に多い。魏の江式の論書表、『隋書』経籍志、鄭樵の『通志』芸文略、『書断』など、みな熹平石経をもって蔡邕一人の書写したものとする説である。
蔡邕一人の書にあらずとする説
先ず蔡邕の書が如何なるものであったかを確定し、その上で、熹平石経の残字をもってこれと対照して決定する外はないが、今日では蔡邕の書そのものが既に明らかでない。
他の碑によって石経の蔡邕の書を確定することも、また石経によって他の碑の書と伝えられるものの真否を判定する方法もないが、今後尚多くの熹平石経の残石が出土するに至ったならば、或は蔡邕一人の書であるか、或は多数の人の手に成ったかは、必ずしも明らかにしがたいことではあるまい。
碑の数について
石経の碑数はいくつあったか、またこれが存佚についても、諸家の記すところは一致しない。
王国維の卓見
熹平石経は、書体についてすら異説を生じ、況んや碑字の行数、毎行の字詰、碑の総数というようなことに至っては殆んど信ずべき定説を得なかったが、近年王国維の『魏石経考』が出て初めて多年の疑念が一掃されることになった。
漢石経の経数、碑数の問題は、王国維のこの考証によって大体その解決を見、その後残石の出土によって、この説の動かすことの出来ないものであることが立証され、多年の懸案もここに解決を見るに至った。
行数字詰について
漢石経の行数と字数についても従来諸家の説は必ずしも一定していない。
漢石経の経数、碑数、行数、字詰等に関する研究は、王国維に至って略々その断案を得、更に新出土の残石とこれに関する羅氏の考証とによって、数百年来学者の論争も、ここに動かすことの出来ない結論に到着したが、その後、残石の出土が相つぎ、他の探求考証も逐次公にされるものが出て来た。
残石の出土について
漢石経は、数度の災厄によってその碑が殆んど散失し、唐の貞観の初めに至って魏徴が残石を収集しようとしたが、得られなかった。
が、宋になって再び残石の出土するものが多く、諸家の著録に散見するものも少くない。
原石宋榻本
明末清初の間になって、北海の孫承沢(万暦20-康煕15、1592-1676)は熹平石経の宋拓本を得て、その研山斎中に収蔵した。
この拓本は、その後、華亭の王氏に蔵せられ、次いで孫星衍に帰した。
朱彝尊は、嘗て宛平の孫氏蔵するところを見たといい、顧靄吉も、僅に尚書、論語、百余字ある拓本を北海の孫氏に蔵せりといっている。
鄒平の張氏本の其後の伝転は不明である。
又別に蔡松原(嘉)の蔵本があり、阮元等に伝わって、最後に端方の収蔵するところとなった。
馬氏玲瓏山館本は黄小松の収蔵に帰した後、また沈均初の蔵する所となり、光緒中(1875-1908)、湖北の万氏の有に帰した。
この端方の蔵本は、今は端方の後人より満洲の衡永氏に帰した。
翻刻本
熹平石経は唐代にその残石を得、その拓本が、歴代諸家の間につぎつぎと手にわたり、これより翻刻したものも少くない。
宋の時に巳に胡宗愈の成都西楼本、洪适の会稽蓬莱閣本、石熙明の越州本があり、明に靖江王府本があり、清朝に入って後は如皋の姜任脩本、北平の翁方綱の小蓬莱閣本、南昌県学本、銭塘の黄易の会稽蓬莱閣本、海塩の張燕昌の石鼓亭本、漢軍李亨特の紹興府学本、陜西の申兆定の関中碑林本、南皮の張之洞の武昌重刻本等を生じた。
但しこのうち銭泳の得たという墨本は、これを南昌県学、紹興府学等に摹刻しているが、それが偽託であることを疑っているものも多い。
清朝における残石の出土
漢の石経は、その残石が宋に出土し、その拓本が諸家に転々として清朝の阮元、黄易諸家に至り、これの研究翻刻等が行われた。
近年に至って三体石経が出土し、次いでまた漢石経の残石が現れ、漢石経の研究史上に更に画期的の新生面が開かれるに至った。
そこで羅振玉氏はその拓本について鈎勒し、この考証をし、『漢熹平石経残字集録』一巻を出したが、その後、更にまた新に拓本を得て補遣一巻を著した。この著録は民国18年(1929)に成り、第一巻はその夏に脱稿し、補遺一巻を秋八月に脱稿した。ここに於いて漢石経の考証は、初めて科学的研究の軌道に乗ることになった。
残石についての羅振玉の考証
羅氏は残石の墨本を得るに従ってこれ考証し、同じ年の冬には『漢石経残字集録』三編嚇巻、補遺一巻を成し、その翌年の春に至って更にこれが第四編一巻及び補遺一巻を写定し、通じて八巻の考証整理を終り、ひと先ずその研究を完成した。
書道博物館収蔵の漢石
漢の熹平石経は、最近、出土するものが凡そ百数十石に至り、その若干は我が国に舶載し、中村氏の書道博物館にも十数石が蔵せられ、孫、黄を去ること数百年後に於いて、親しく漢石の実物を手にとってみることができる。
新出土残石の研究と著録
新出の熹平石経については羅氏の外、研究者が続出し、馬衡(叔平)氏は民国16年(1927)に『集拓新出漢熹石経残字』四冊を、呉維孝(峻甫)氏は同年に『新出漢魏石経考』四巻を、白堅(堅甫)氏は民国19年(1930)に『漢石経残字集』一巻を、関百益氏は『漢石経残字譜』一巻、屈万里氏は『漢魏石経残字校録』一巻を出した。
この外、雑誌に見られる多数の論文がある。
しかしながら新出の残石中には、往々偽作のものさえ見られるようになり、石経について論じようとするものは先ずその点から弁じなければならないという問題まで生じたが、この残石の出土によって、その書体、経数、碑数、行字等、かつて疑問とされていた多くの懸案が、羅振玉によって、殆んど十の八、九まで解決されるようになったことは実に幸といわねばならない。